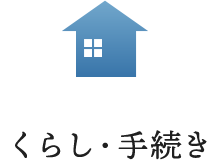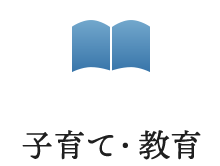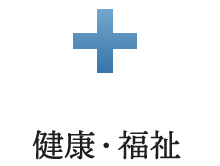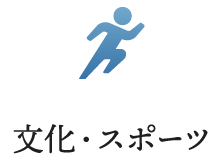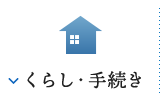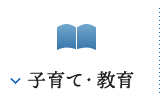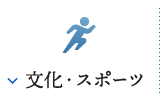スクールESDくさつプロジェクト 老上中学校よしずづくり
更新日:2025年7月7日
スクールESD
ESDとは、SDGs(持続可能な開発目標)の実現に向けた教育のことをいい、
草津市では、「スクールESDくさつプロジェクト」として、
市内小中各校で様々な地域課題の体験学習を通して、児童・生徒たちが主体となって
かかわることで、地域社会の一員である意識と行動力を身に着けることを目指しています。
老上中学校 三方よし学習

老上中学校2年生は、「世間よし 琵琶湖よし みんなよし、老上中生三方よし」と題した学習を昨年始めました。
世間に貢献できてよし、琵琶湖の環境もよし、そうすることで、みんなが楽しく幸せに過ごせてよし、を目指します。
滋賀県について、琵琶湖について、ヨシについて。
それぞれのテーマをさらに細分化し、環境や水、活用などについて、詳しく調べてまとめ、スライドショーを利用して班ごとに発表しました。
ヨシと琵琶湖の環境について

琵琶湖に茂るヨシは琵琶湖の環境を守るため大切な役割を果たします。
刈り取り焼くことで、害虫や雑草の駆除ができ、その灰は肥料になります。
逆に刈り取らず、放置すれば、二酸化炭素の吸収量が減ったり、メタンガスが発生したりします。
水質の悪化や動物の住みかの減少にもつながるため、毎年刈り取ることが重要になります。
そこでヨシ刈り!

ヨシを刈ることの重要性は学びました。
毎年ヨシ刈りを続けるにはどうすればよいか。
ヨシ刈りをする人材は確保できるのか。
刈ったヨシを何かに利用できないか。
実際にヨシ刈りをしてみよう!
そして1年生の1月、近江八幡市の西の湖で実際にヨシを刈りました。
よしずを作ろう!
生徒たち自身が刈り取ったヨシを使ってよしずを作ります。
指導してくださるのは、県が推進するMLGs(マザーレイクゴールズ)にも深くかかわり、環境保全や地域資源の活用に取り組まれている、非営利活動法人まるよしのみなさん。
生徒たちが刈り取ったヨシの乾燥、保管をして、当日に備えてくださいました。
ヨシを準備します
よしずの完成イメージは、幅2.7メートル、長さ1.5メートル。
これを各クラス4枚作ります。
1枚に使用するヨシは約120本。
各クラス4束ずつ体育館に運び込みます。
ひもも用意します
今回ヨシをつなぐひもはシュロ縄を使いました。
これを組みやすくするために竹の筒に通し、巻き付けます。
竹筒にひもをまく方法も教えていただきます。
さあ作りましょう
ひもを編む人3人、
ヨシがまっすぐになるよう押さえる人2人、
ヨシを差し入れる人1人の6人一組で作り始めます。
1本おいてはひもを編み、
ヨシが反らないように押さえ、
次のヨシを差し入れる。
差し入れるヨシは、上下を見て太い方が左右交互に来るようにすることで
均等なよしずができます。
これを繰り返し、形ができていきます。
メイキング
みんなで息を合わせて作っています
完成!
みんなで作ったよしずは、クラスごとに教室の日当たりのよい窓側に設置され、
置いたところと置いていないところでの、温度や湿度の変化を観察します。
この結果をまとめ、環境学習に生かしていきます。
今回実際にヨシを手に取り、ひもを編みこんで作り上げた経験から、
新しい発想でヨシを生かした商品が考え出されるかもしれません。
商品化など、ヨシの用途が増えれば、刈り取る機会も増え、
ヨシ原や琵琶湖の環境を守ることにも役立つのではないか、
学習成果発表が楽しみです。
昔は夏の風物詩といわれていたよしず。
最近は見る機会も減りましたが、
中学生たちによって新たな価値が見つけられるかもしれません。