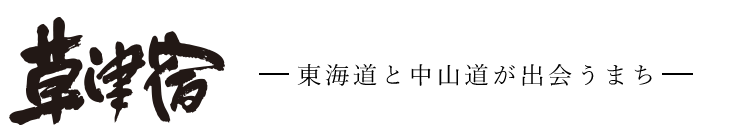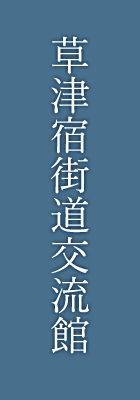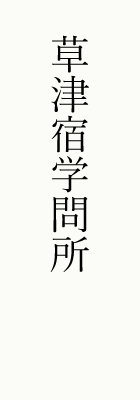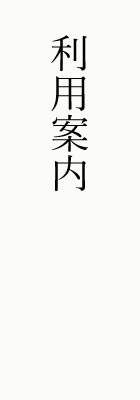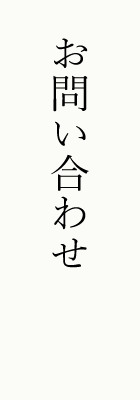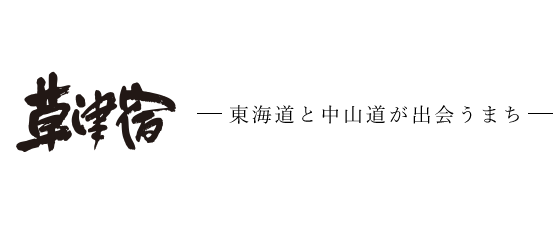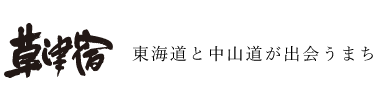所蔵品紹介
更新日:2019年4月1日
大福帳

本陣の利用者の名前や下賜金、その日その日に草津宿を通行した主な人物から、奉公人の給金まで、代々の当主が記した記録です。
元禄5年(1692)から明治7年(1874)に至るまでの183年間分、計181冊が残されています。
元禄12年(1699)には浅野匠頭と吉良上野介が9日違いでこの本陣を利用しているなど、歴史上有名な人物の名前も散見できます。
関札
本陣に誰が休泊しているのか知らせるための札で、本陣の表門脇や、宿場の入口に掲示しました。
草津宿本陣には木製関札約460枚、紙製関札約2900枚が残されています。
襖絵
皆川淇園襖書
江戸時代の京都の儒学者、
向上段の間に設えられています。
寒山拾得図

岸派の二代目岩岱によるもの。
中国唐代中期の高僧、拾得と寒山二人から取材し、描かれています。住居部に設えられていました。
※現在、展示は行っていません。
平戸焼茶椀
平戸藩主・松浦
「贈草駅三少庵主人 平戸城主自書」(草津宿・三少庵の主人に贈る 平戸城主が自ら記す)と染付られており、本陣当主と利用者の交流の様子がうかがえます。
調度品

明治天皇は6回の草津通行のうち、この本陣で5回休泊しており、そのうち2回目の行幸時に使ったとされる調度品が多数残されています。
皇女和宮の食事
皇女和宮は、文久元年(1861)14代将軍徳川家茂に嫁ぐため京を発ち、10月22日に草津宿本陣で昼食休憩を取りました。
当時の記録に見られる献立を再現しました。
お問い合わせ
教育委員会事務局 史跡草津宿本陣
〒525-0034 滋賀県草津市草津1丁目2番8号
電話番号:077-561-6636
ファクス:077-561-6636