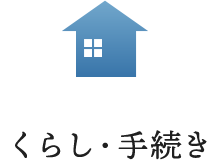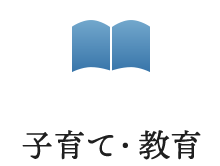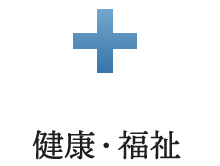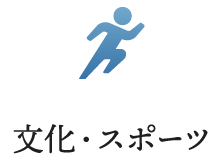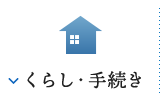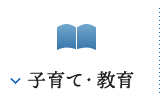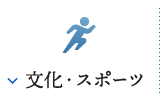生活保護制度
更新日:2026年1月28日
生活保護制度は、資産、能力等を活用してもなお生活に困窮する者に対して、憲法第25条に規定する理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を無差別平等に保障するとともに、その自立を助長することを目的としており、国民が安心して生活を送るために欠くことのできない「国民生活の最後のセーフティネット」といえます。
これらのことから、生活保護は国民の権利とされており、生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに窓口までご相談ください。
![]() 生活保護のしおり(令和8年1月時点)(PDF:640KB)
生活保護のしおり(令和8年1月時点)(PDF:640KB)
生活保護制度の基本的な考え方
生活保護法には、制度を運用するにあたって、遵守しなければならない基本原理と、制度を具体的に実施する場合の原則が定められています。生活保護制度の設計や基準設定は国の責任において実施されていますが、運営については各実施機関が担っています。各実施機関においては、生活保護受給者の実情に応じて、生活保護受給者がその能力を最大限に発揮し、その能力に応じた自立(経済的自立、日常生活自立、社会生活自立)が果たせるよう支援を実施します。
なお、生活保護の決定実施にあたっては、他法他施策の優先活用が前提となっています。
原理
国家責任による最低生活保障の原理
この制度は、生活に困窮する国民の保護を、国がその直接の責任において実施し、単に最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者の将来における自立の助長を図ることを目的としています。
無差別平等の原理
すべての国民は、要保護状態になった原因の如何は一切問わず、法律に定める要件を満たす限り、無差別平等に生活保護を受けられることになっています。
最低生活保障の原理
この制度で保障する最低生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないこととされています。
保護の補足性の原理
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われます。なお、親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって、生活保護を受給できないということにはなりません。
原則
申請保護の原則
この制度による保護は、要保護者自身か、その扶養義務者、あるいは同居の親族の申請により、はじめて開始されることを原則としています。
ただし、急病等の急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、職権により、必要な保護を行うことができることになっています。
基準および程度の原則
保護の具体的な実施にあたっては、厚生労働大臣が保護の基準を定め、要保護者の需要を基にして、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うことを原則としています。
また、この基準は、国民の最低限度の生活水準を示すものであり、要保護者の年齢、世帯構成、所在地域その他保護の種類に応じ、必要な事情を考慮して定められることになっています。
必要即応の原則
要保護者の生活は、年齢や健康状態など、個々の事情の相違を考慮して、有効かつ適切に行われることを原則としています。
世帯単位の原則
我が国の生活実態に鑑み、世帯を単位として経済生活が営まれていることから、保護の要否や程度を決定するときは、世帯を単位とすることを原則としています。
生活保護の手続、種類
生活保護は、原則として申請に基づいて開始されることとなっており、本人またはその扶養義務者などが、保護の実施機関である草津市福祉事務所に申請することとなっています。
保護の申請があれば、保護の実施機関は、生活に困窮することになった経緯をはじめ、扶養義務者の状況、資産などを調査し、保護を開始するかどうかを決定することになります。
保護の種類
| 扶助名 | 内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 衣食その他日常生活に必要な費用 |
| 住宅扶助 | 家賃、間代、地代あるいは住宅の維持補修に必要な費用 |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な費用 |
| 医療扶助 | 医療費 |
| 介護扶助 | 介護サービスを受けるために必要な費用 |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 |
| 生業扶助 | 小規模事業を営むための費用、あるいは技能修得、就職支度に必要な費用 |
| 葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
注記:世帯の状況等により適用できる扶助の種類が異なります。適用の可否については事前に草津市福祉事務所(生活支援課)へご相談ください。
保護の要否と程度
保護の要否と程度は、最低生活費と収入との対比で決定されます。なお、最低生活費は、社会、経済の情勢により国が決めることになっています。
保護の方法
保護の方法には居宅保護と施設入所による保護があります。
居宅保護
被保護者に対する扶助は、その者の居宅において行うことが原則です。また、その扶助は金銭給付を原則としていますが、医療扶助や介護扶助など金銭給付が適当でないものは、直接に医療や介護サービスなどを受けてもらうこと(現物給付)により支給されます。
施設保護
居宅生活が困難で、事情によっては施設入所によらなければ法の目的が達せられない場合があり、この場合は施設入所により保護を行います。
被保護者の権利と義務
保護は最低生活の維持のための給付であり、またその費用はすべて国民の税金により賄われていますから、それらに対応して被保護者には、特別の権利が与えられている一方、義務も課せられています。
権利
不利益変更の禁止
正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。
公課の禁止
保護金品を標準として、租税その他の公課を課せられることはありません。
差押えの禁止
既に給付を受けた保護金品またはこれを受ける権利を差し押さえられることはありません。
義務
譲渡の禁止
保護を受ける権利を譲り渡すことはできません。
生活上の義務
被保護者は、常に、その能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他の生活の維持、向上に努めなければなりません。
届出の義務
被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、または、居住地や世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関に届け出なければなりません。
指示等に従う義務
保護の実施機関は、被保護者に対して生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示を行うことができることになっています。
被保護者は、保護の実施機関からこれらの指導または指示を受けたときは、これに従う義務があります。
なお、これらの指導または指示があったにもかかわらず、これに従わないときは、保護の実施機関は保護の変更、停止または廃止をすることができることになっています。
生活保護に関する相談、申請窓口
健康福祉部生活支援課 電話:077-561-2361
生活保護にかかる不服申立てを行う場合
滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課 電話:077-528-3513
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康福祉部 生活支援課 生活保護係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2361
ファクス:077-561-2482