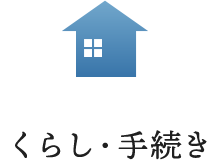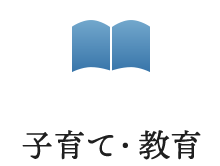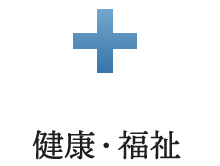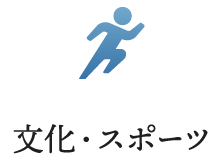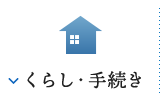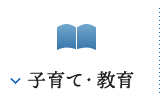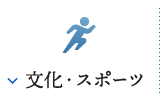昔の道具を調べよう
更新日:2023年6月6日
食べる
| 道具の名前 | 説明 | 調べてみよう |
|---|---|---|
| 食べ物を煮炊きしたり、お湯を沸かしたりするもの。今でいうコンロ。京都や草津では「おくどさん」と呼んでいた。 | 火吹き竹 | |
| かま(PDF:67KB) | 昔から生活が豊かになることを「鍋釜(なべかま)がにぎわう」という。このように鍋や釜は生活の基本で、何はなくともこれだけは備えねばならないものとされてきた。羽があるので「羽釜(はがま)」とも呼ばれる。 | 囲炉裏(いろり) |
ふたのついた器を「ひつ」という。炊いたご飯を入れるひつを「飯ひつ」というのだが、「おひつ」が一般的な呼び方になった。通気性があるので、水気を吸収すると同時に保温性もある。「さわら」「ひのき」「すぎ」という種類の木を使って作っているので香りがよく、一度おひつに移した飯は直接釜からついだ飯よりも味が良い。また、抗菌作用がある。寒い冬には「わら」などで編んだ「ふご」や「いずめ」と呼ばれる保温用機に入れておいた。 | えじこ | |
| 七輪(PDF:76KB) | どこでも使えて持ち運びできるコンロ。燃料の炭を入れ、下のほうにある空気が通る穴を開けたり閉じたりすることで火力を調整する。火を起こす「火吹き竹」や、「渋団扇(しぶうちわ)」が使われた。 | 火吹き竹 |
| 折りたたみ式の食卓。ちゃぶ台で食事をするようになると、個人で食器や膳(ぜん)を持っていたそれまでの風趣(ふうしゅ)が次第に消えていった。 | 箱膳(はこぜん) |
その他に...
- 炊飯器(すいはんき)の移り変わり
- 給食の移り変わり
- お弁当箱の移り変わり
- 膳(ぜん)の役目
なども調べてみよう!
住む
| 道具の名前 | 説明 | 調べてみよう |
|---|---|---|
| 何人かが同時に温まることができる暖房具(だんぼうぐ)。今のように机はなく、布団をかけて使った。 | こたつの移り変わり | |
| 夜、寝るときに布団の中で冷えた体や足を温める道具。豆炭を中に入れて使用する。そのまま使うとやけどをするので、布袋などにいれて使う。 | ||
| 器の中に湯を入れて栓(せん)をし、やけどをしないように布にくるんで使っていた。朝に覚めてぬるま湯となったもので、よく顔を洗っていた。ブリキ製もある。 | ||
| 中に灰を入れ炭火を置いて、部屋や手を温めるための器具。中に五徳(ごとく)という道具を置いて、その上にやかんを乗せて湯を沸かしたりもした。 | 火ばさみ | |
| 電話(PDF:76KB) | 明治時代は壁(かべ)かけ式の電話が使われていた。電話をかけるとまず「交換局(こうかんきょく)」につながる。そこで、「交換手(こうかんしゅ)」に相手の電話番号を伝えるとつないでくれた。昭和時代になると、自動交換が始まり、自分で相手の電話番号を「ダイヤル」するダイヤル式卓上(たくじょう)電話機が使われ、黒電話が主流であった。その後、プッシュ式の電話が登場した。 | 公衆(こうしゅう)電話 |
| 扇風機(せんぷうき)(PDF:123KB) | 手で動かす扇風機はすでに江戸時代にあった。うちわを軸(じく)に取り付け、それを手で回すもので、「団扇車(うちわぐるま)」と呼ばれていた。電気で動く扇風機は、明治26年にアメリカから輸入(ゆにゅう)され、次の年に国産第1号が発売された。 | |
| 蚊帳(かや)(PDF:103KB) | 蚊を避けるためのもの。夜寝るときに使用した。麻(あさ)の布や紙で作られた蚊帳がある。蚊帳がない家では、蚊遣(かやり)という木くずなどを燃やした煙で蚊を追い出した。 |
農/漁業
| 道具の名前 | 説明 | 調べてみよう |
|---|---|---|
| 鋤(すき)(PDF:29KB) | スコップのように足で土中にふみ込み、田畑の土を耕(たがや)す道具。 | |
| 犂(すき)(PDF:34KB) | 牛馬に引かせて田畑を耕す道具。中国や朝鮮半島から伝わった。 | |
| 田打くるま(たうちぐるま)(PDF:41KB) | 水田の除草(じょそう)用具。この道具ができたことで、作業がはかどり、一日に八反歩もの草取りができたことから、「ハッタンドリ」や「ハッタンボ」という名前で各地に広がった。 | 草取づめ |
| 足ふみだっこくき(PDF:102KB) | かり取って感想(かんそう)させた稲穂(いなほ)から「もみ」を落とすのに用いた。 | 板み |
| とうみ(PDF:78KB) | ハンドルを回して風をおこし、お米とゴミを分ける道具。上からお米を入れると、重たいお米は下に落ちるが、実っていない軽いお米やゴミはちがうところから出るようになっている。 | |
| 万石通(まんごくどおし)(PDF:96KB) | もみすり後の玄米(げんまい)ともみがらを選別(せんべつ)する農具。上にある漏斗(ろうと)からもみがらのまじった玄米を数まいの金あみの上にながすと、玄米だけが下に落ちる。 | 千石通し(せんごくとおし) |
| 馬鍬(まんが)(PDF:69KB) | 田畑の土を細かくする道具。水田では、牛馬に引かせて、田植え前の水を張った田の土を細かく平らにならす代掻き(しろかき)に使った。 | |
| うけ(PDF:52KB) | 魚類、カニ、エビなどをその習性を利用して捕獲(ほかく)するため、河川、湖泥、用水路、沿海の水中に沈めておく仕掛け。 |
着る
| 道具の名前 | 説明 | 調べてみよう |
|---|---|---|
| 洗たく板(PDF:83KB) | 衣服などを洗うのに使う、みぞをほった縦長の板。たらいの中に入れ、板をななめにして使用する。これが使われる前は、石の上で手でもんだり、足でふみ洗いをしたり、洗たくぼうでたたいて洗う方法がとられていた。 | 洗たくばさみ |
| ローラー式せんたく機(PDF:68KB) | せんたく物と洗剤を入れてスイッチを入れると、機械(きかい)が自動でせんたくをする。洗う強さや時間はダイヤルを回して決めた。せんたくが終わると2本のローラーにせんたく物をとおし、ハンドルを回すと脱水(だっすい)できた。 | |
| 二層式せんたく機(PDF:63KB) | 左側で洗たく物を洗い、洗たくが終わったら右側の水槽(すいそう)に入れて脱水(だっすい)する。洗う強さや時間はダイヤルを回して決める。脱水も自動でできるようになったが、洗たく物を移すのは人の手でやっていた。 | |
| ひのし(PDF:88KB) | 中に炭を入れて布に当て、その熱で布のしわを伸ばしたり、仕立ての仕上げに用いる道具。 | アイロンのうつり変わり |
| ミシン(PDF:123KB) | ふみ板をふむ力を、ベルトの回転を通して伝え、原動力としたミシン。 |
運ぶ
| 道具の名前 | 説明 | 調べてみよう |
|---|---|---|
| 大八車(PDF:126KB) | 人力で引く大型の荷車。江戸時代初期から江戸時代を中心に使われるようになった。米などの収穫物、石材、木材などさまざまな運搬に用いられた。大正時代以降は馬車や牛車の使用が多くなり、またトラックの普及もあって徐々に減少した。 | |
| 荷車(PDF:208KB) | 重いものを乗せて運ぶ車。一般には人力で引く車をさし、馬に引かせるのを馬車、牛に引かせるのを牛車という。 | |
| 風呂敷(PDF:71KB) | 現在も使われている。物を包んで運ぶのに用いる方形の布。これで頭部をおおい、頭巾(ずきん)として使うこともあった。 |
娯楽
| 道具の名前 | 説明 | 調べてみよう |
|---|---|---|
| オルガン(PDF:107KB) | 足元にあるペダルで風を送って音を鳴らす楽器。今は、電気モーターで風を送っている。 | パイプオルガン |
| ちく音機(PDF:87KB) | ハンドルを回してゼンマイをまくと、レコードが回る。針(はり)がレコードのみぞを通る時の細かい振動(しんどう)で音が出る。 | 音楽プレイヤー |
| メンコ(PDF:213KB) | 少し分厚い紙で作られた物。丸や四角の形がある。牛乳びんのふたやヨーグルトびんのふたでも遊ばれた。 | |
| お手玉(PDF:111KB) | 小さな布のふくろの中に小豆(あずき)や数珠(じゅず)玉を入れ、数個を一組とする遊び道具。 | |
| おはじき(PDF:74KB) | ガラスでできた円ばん型のおもちゃ。ガラスの前は、木の実や貝がら、小石などで遊んでいた。今はプラスチック製のものもある。 |
学校
| 道具の名前 | 説明 | 調べてみよう |
|---|---|---|
| 教科書(PDF:884KB) | 学校が明治時代にできたときに、いろいろな教科書がつくられたが、全国共通にするために国がつくった教科書になった。 | |
| 屋根がわら(PDF:97KB) | 昔の学校は、木造で、かわらの屋根でした。今はコンクリート製です。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ