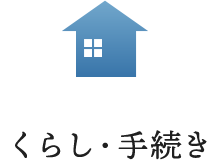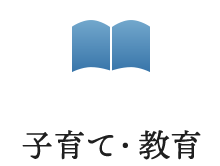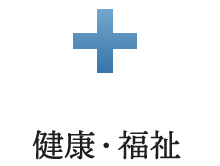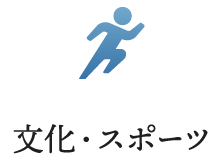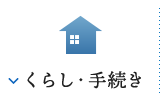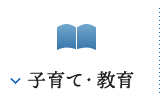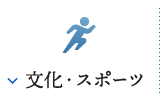司書のおすすめ(「図書館だより」より)
更新日:2026年1月26日
毎月発行している「図書館だより」に掲載した「司書のおすすめ」です。本選びの参考にしてください。
資料によっては、貸出中の場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 『滋賀県妖怪事典』峰守 ひろかず/著(図書館だより2026年2月号より)
- 『シンプルな豊かさ 癒しと喜びのデイブック 1月~6月/7 月~12月』 サラ・バン・ブラナック/著 延原 泰子/訳(図書館だより2026年1月号より)
- 『東京裏返し 社会学的街歩きガイド』 吉見 俊哉/著 (図書館だより2025年12月号より)
- 『装丁物語』 和田 誠/著 (図書館だより2025年11月号より)
- 『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』川内 有緒/著(図書館だより2025年9月号より)
- 『こどもになって世界を見たら?』 こどもの視点ラボ/著(図書館だより2025年8月号より)
- 『スナーク狩り』 ルイス・キャロル/作 ,トーベ・ヤンソン/絵, 穂村 弘/訳(図書館だより2025年7月号より)
- 『空と湖水 夭折の画家 三橋節子』 植松 三十里/著 (図書館だより2025年6月号より)
- 『世界のエリートは なぜ「美意識」を 鍛えるのか?』山口 周/著(図書館だより2025年5月号より)
- 『本を読んだことが ない32歳が はじめて本を読む』かまど/著 、みくのしん/著(図書館だより2025年4月号より)
- 『ダメじゃないんじゃないんじゃない』 はらだ 有彩/著(図書館だより2025年2月号より)
- 『幸せってなんだっけ?世界一幸福な国での「ヒュッゲ」な1年』ヘレン・ラッセル/著,鳴海 深雪/訳(図書館だより2025年1月号より)
『滋賀県妖怪事典』(外部リンク)峰守 ひろかず/著(サンライズ出版)2025年刊 一般書388.161【両館所蔵】
縁あって著者の峰守ひろかず氏からお話を聞く機会を得た。峰守氏は怪異ものを得意とする小説家だが、実は、図書館で徹底的に資料集めをしてから書くという図書館マスター。本書の執筆でも図書館をフル活用して調査したと伺い、図書館に携わる者として大変誇らしい思いがした。
本書の特筆すべき点は、「事典」としての機能性を強く念頭に置いていることである。参考文献リスト、地域別索引、種類別索引を完備していることはもちろん、著者の見解や創作を一切付け足すことなく、地域の伝承に関する本や報告書などの資料の文章を可能な限りそのまま要約して掲載することにこだわり、妖怪調査に真に役立つことを願って編まれている。
河童や天狗などのメジャーな妖怪は全国的に記録が多く残されているので、滋賀県内にもやはり広範な地域に多くの伝承が残る。しかし、出現する地域が少ないといわれる妖怪の伝承もまた、数多く県内に伝わっていることに、著者はとても驚いたそうだ。例えば、『ゲゲゲの鬼太郎』でおなじみの「すなかけばばあ」は伝承自体が少ないそうだが、県内に3例もあり、しかもその一つは草津に繰り返し現れていたという伝承である。
表紙絵や挿画を担当した漫画家の久正人氏は、知る人ぞ知る「怪人デザイナー」でもあり、特撮ヒーローの敵役のキャラクターデザインを手掛けている人物だ。著者とは怪異好き仲間であり、そのよしみで描いてもらうことになったという。点数は多くないが、時折挿し込まれている妖怪たちの絵は迫力満点で、私たちの想像を掻き立ててくれる。
草津にはどんな妖怪が現れたのか?を調べてみるのもよし。有名な妖怪が滋賀県内ではどんなふるまいをしていたのか?を調べてみるのもよし。普段から通っているこの場所に、そんな妖怪がいたなんて!ときっと驚くことだろう。(南館 大西)
『シンプルな豊かさ 癒しと喜びのデイブック 1月~6月/7 月~12月』(外部リンク)サラ・バン・ブラナック/著 延原 泰子/訳(早川書房)1997年刊 一般書159.6【本館所蔵】
新しい年が始まる1月、「今年はこんな年にしたい!」と誓いを立てたり、目標に向かって計画を準備する人も多いのではないでしょうか。そんな意気込み空しく、立てた計画に縛られ過ぎて身動きできなくなったり、スケジュールを詰め込み過ぎて窮屈な日々を過ごすことにならないように、自分を見つめ直して、背筋を伸ばし、深呼吸するような1月を過ごしてみませんか。
本書は、外見や見た目の豊かさではなく、自分自身の豊かさを、1年を通じて感じていこうと日記形式で「シンプルな豊かさ」の提案が綴られています。例えば、1月7日には、【あなたは今どのぐらい幸せですか?】と、タイトルがあり、ジョアナ・フィールドの次の言葉が紹介されています。―自分の幸せな時がはっきりとわかっているなら、自分の人生に必要なものもおのずとわかる―。1年のはじまりの1月の章には、「感謝」、「簡素」、「秩序」、「調和」、「美」、「喜び」に込められた「シンプルな豊かさ」の6原則についての説明がされています。そして、見過ごされがちな単純な楽しみこそが「シンプルな豊かさ」の始まりだと著者は語ります。2月は、本当の自分を見つけることについて。それ以降の月は、家庭、仕事、お金、美、ファッション、個人的な趣味などの日常生活の中でどう自分と向き合うかについて考えます。
読者は、シンプルで心豊かな生活を実感できる提案の文章や、さりげない一言、紹介されている引用文に共感したり、ハッとさせられたりしながら読み進むうちに、心が穏やかになって癒されていく自分に気づかされます。
1月14日の頁に「感謝の日記」という提案があり、私も試してみました。毎晩休む前に、その日ありがたいと思ったことを5つ書きます。思い浮かばない時は、自分や家族の健康、今日が終わったことなどを書くだけです。先ずは1か月続けてみてください。心の中に何か変化を感じることでしょう。本当に大切なものを見極め、新しい扉を開くのはあなたです。(本館 二井)
『東京裏返し社会学的街歩きガイド』(外部リンク)吉見 俊哉/著(集英社)2020年刊 一般書361.78【本館所蔵】
「ブラタモリ」といった街歩き番組が人気となり、健康ブームもあって街を歩く機会が増えた人も多いのではないだろうか。本書は、観光的な意味での街歩きではなく、「時間論としての街歩き」を提唱し、「モモ」を隠れた随伴者として東京都心を7日間にわたり歩くことをコンセプトとしている。
「モモ」とは、ミヒャエル・エンデの『モモ』に登場する主人公の少女のことである。『モモ』は、言わずと知れた児童文学の傑作であり、この物語は現代資本主義の時間論に対する批判であると言われている。しかし、著者がこの物語に着目したのは、それが「近代を超える時間論であると同時に都市論でもあるから」である。物語では、「灰色の男たち」から人々の時間を取り戻す「モモ」の冒険が描かれているが、開発の波が「モモ」の住む廃墟となった円形競技場まで迫っているところは、現代の都市開発の波を連想させる。
本書では、1964年の東京オリンピック前後の都市改造で周縁化された地域である都心北部に焦点を当て「移動の速さ」や「非日常的な時間の場」などを軸に街歩きを進めている。そして、高度経済成長に象徴されるような、過去を切り捨てゼロから新しいものを生み出す開発ではなく、過去の資産を再生し、都心北部の諸地域をつないで東京の文化の中心にする構想を提案している。
7日間の「ガイド」に通底しているのは「開発主義の東京から、再び人間的時間を取り戻す」ことである。東京都心の地理に明るくないとイメージがわきにくいところがあるだろうが、歴史を紐解きながら進んでいく「ガイド」に著者の見識の深さを感じる。そして、この本を携えながら都心の街歩きをしたいと思わされ、徒歩や自転車、路面電車などゆっくり移動することの価値を見出すことができる。「モモ」という隠れた随伴者を連れて、自分も身近な街をゆっくり歩いてみたいと思った。(南館 杉谷)
『装丁物語』(外部リンク)和田 誠/著(白水社)1997年刊 一般書022.57【本館所蔵】
これまで48年という長きにわたって、和田誠氏が手掛けたイラストが採用されてきた「週刊文春」の表紙が、今年の9月からついに変更になった。日常の何気ない風景を切り取ったイラストは、さりげないのに不思議と深く心に残り、雑誌のアイコンとしての役割をしっかりと果たしてきた。イラストレーターとしてあまりにも著名な氏だが、その仕事の内容は非常に多岐にわたり、本の装丁も数多く手掛けている。そんな装丁の仕事の様子や、仕事の中で出会った印象的な人や本、著者自身が仕事をする上で大切にしていることなどが親しみやすい文章で綴られているのが本書である。
紙や画材の選び方、どのような道筋で本の装丁を決めるのか、その本の内容や面白さを装丁からどのように伝える工夫があるのか、装丁をする中でいちばん悩ましいことは何かなど、どれも興味深い話ばかりで、読み進めるうちに手近にある本の装丁を改めてじっくりと眺めてみたくなった。カバーからすでに本文が始まっている本や、帯を外すまではあえて写真が見えないように作られた本など、遊び心たっぷりの変わった工夫やびっくりするような仕掛けのつまった装丁の本も多い。「そんなに面白い装丁の本があるんだ」「あの本にそんな秘密が隠されていたんだ」と何度も驚き、実際にその本を手に取って読んでみたいと感じることもたくさんあった。
本書を読み進めるほどに、著者が愛情や手間暇をかけて、何よりも心から楽しみながら、本や装丁と真摯に向き合ってきたことが伝わってくる。それほどまでに愛を込めてこの世に送り出された本は、きっと幸せに違いない。図書館司書として、そんな本が図書館にやってきてからも、たくさんの人の手に取られ、少し傷んだとしても丁寧に修理され、できるかぎり幸せに過ごせるようにすることは使命だと思っている。(本館 福田)
『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』(外部リンク)川内 有緒/著(集英社インターナショナル)2021年刊 一般書706.9【本館所蔵】
タイトルを見て、「目の見えない白鳥さん」とは一体何者なのだろうか、目の見えない方とアートを見に行くとはどんなかんじなのだろうか、と興味が湧き、思わず手に取りました。
本書は、著者の川内さんが、全盲の美術鑑賞者・白鳥建二さんと出会い、様々なアートを巡る体験の中で感じたことや見えてきたことが綴られています。
「白鳥さんと作品を見るとほんとに楽しいよ!」と友人に誘われた川内さんは、初めて白鳥さんと美術館へ行き、白鳥さんから「じゃあ、なにが見えるか教えてください」と質問され、絵の形や色、描かれているもの、絵の印象などを伝えていきます。すると、絵の細部にまで目がいくようになり、これまで見えてこなかったものが見えてきたり、同じ絵を見ているのに感じる印象が友人と全く違うことに気づきます。その経験をきっかけに、川内さんは、白鳥さんと度々アート巡りをするようになり、その中で少しずつ「白鳥さん」という人の生き方についても知っていきます。
アート鑑賞の様子が会話形式で綴られており、感じたことを自由に言い合う様子がおもしろく、読者も会話を楽しみながら一緒に鑑賞しているような気分になります。私自身もアートが好きでよく美術館へ行くことがありますが、一人で静かに見ることが多く、見え方を人と共有し、いろんな意見を感じながら絵を見るという鑑賞スタイルが新鮮で、白鳥さんとアートを見に行きたくなりました。
本書を読む前は、目の見えない方がアートを見に行くということに意外性を感じていたのですが、読んだ後には、アートは誰でも楽しめるものだと感じました。本書は、アート鑑賞の記録に留まらず、「見る」ということ、障害のこと、生きることなどについても新たな視点をもたらしてくれる作品だと感じました。本書を通して、新しい形のアート鑑賞を体験してみてください。(本館 神村)
『こどもになって世界を見たら?』(外部リンク)こどもの視点ラボ/著(トゥーヴァージンズ)2025年刊 一般書376.11【本館所蔵】
大人になって、こどもの頃に大きく感じた遊具、いつも使っていた机や椅子が、こんなに小さかったかな?と感じたことはありませんか?誰もが経験してきたはずなのに、いつのまにか忘れてしまったこどもの目線をユニークに紹介した本があります。
本書は、こどもの当事者視点を研究している「こどもの視点ラボ」が、こどもが見ている世界を大人に当てはめて数値化し、実験を行っています。例えば、新生児の頭は身長の4分の1程度ありますが、これを大人に換算すると、身長180センチ体重70キロの男性の場合、なんと21キロもあるそうです。また、小学生のランドセルの重さについても研究を行っています。小学1年生の荷物の平均は5.7キロもあり、これを大人が背負うとすると、18.9キロの重さにもなります。他にも「こどもの視力体験。赤ちゃんにはこんなふうに見えていた!」「怒る大人はどれほどこわい?」等、全部で12の研究が紹介されています。おもしろいのが、数値を出すだけでなく、実際に大人の4分の1サイズの大きさの頭を作ってかぶってみたり、大人用にランドセルを作って学校関係者に背負ってみてもらったりと、こどもの気持ちにより近づける試みをしているところです。
なぜこのような研究を始めたかというと、こどものことが全然分からない!と思ったからだそうです。子育て本を読んでも検索の沼にはまっても分からなかったこどものことを、こどもになってみることで理解しようと思い、立ち上げられたのがこどもの視点ラボです。
こどもたちはこんなに大変な毎日を過ごして成長していくのだということを知り、一生懸命何かに取り組んでいる姿がより愛しく思えてきました。身近な存在のこどもたちの奥深い世界を楽しみながら学ぶことができます。(本館 塩崎)
『スナーク狩り』(外部リンク)ルイス・キャロル/作 トーベ・ヤンソン/絵 穂村 弘/訳(集英社)2014年刊 一般書931.6キ【南館所蔵】
最初に断っておくと、本作に意味を求めてはいけない。なにしろ、作者はノンセンス文学の代名詞ルイス・キャロルである。「なんだかわけがわからない」を楽しむ本もあるのだなぁと鷹揚にかまえてお付き合い願いたい。
本作は、ヘンテコな登場人物と巧みな言葉遊びで有名なキャロルの処女作『不思議の国のアリス』のしばらく後に発表された長編詩で、原文では韻を踏むように書かれている。船長ベルマンと8人+1匹の乗組員が、誰も見たことがない怪物「スナーク」を捕まえるため、まっしろな海図を手に冒険するという筋書きはあるものの、不思議な言葉の並びが読者を翻弄する。人の噂でしかない「スナーク」を追いかけるさまは社会風刺にも思えるが、作者の真意はわからない。
トーベ・ヤンソンの挿絵も「なんだかわけがわからない」世界観にぴったりだ。『アリス』にも出てくる架空の動物「バンダースナッチ」に襲われるシーンは恐ろしく、乗組員たちの表情はどこかコミカルに、細かく描かれている。そうすると「スナーク」もどこかに描き込まれているのではないかと探すのだが、いるような気もするし、いないようにも思えて、確信は持てない。
調べてみたところ、『アリス』が生まれた頃、日本は幕末。出版ブームで読書人口が一気に増え、長編小説が次々に出版された後、川柳や狂歌、判じ物のような言葉遊びを楽しむ本が流行した。日本とイギリス、文化も風土もまったく違う大海を隔てた国で、同時代に同じような言葉遊びの本が生まれたのだ。
そして今度は、現代短歌の歌人穂村弘が、日本古来の長歌形式を借りて五と七のリズムで、「なんだかわけがわからない」のはそのままに、洒脱に訳している(なぜ同じ言葉を三度繰り返すのかは読んでのお楽しみ)。
それを私が偶然本棚で見つける、不思議な巡り合わせ。本に携わる者として、これほどロマンを感じる瞬間はないのである。(南館 大西)
『空と湖 水夭折の画家三橋節子』(外部リンク)植松 三十里/著(文藝春秋)2019年刊 一般書913.6ウ【両館所蔵】
本書は、画家としての道を歩み始めた三橋節子が病で右手を切断した後、絵筆を左手に持ち替え、夫と幼い子ども達を残して35歳で早世した人生を小説化したものだ。著者は様々な資料を読み解き、資料にない二人の馴れ初めや厳しい闘病生活などは夫で大津市在住の画家、鈴木靖将さんから直接伺ったという。妻として母として揺れ動く繊細な心と画家としての人生を全うしようとするひたむきな情熱が歴史小説家の目を通して丁寧に描かれている。
物語は、5歳年下の画家である夫との純粋で微笑ましい馴れ初めから始まる。二人は、思いのすれ違いや心の葛藤を乗り越え結婚。二人の子どもにも恵まれ、夫婦共に画家としても認められて仕事も軌道に乗り、まさにこれからという幸せな時、節子は苛酷な病に冒されていることを知らされる。夫は、妻が画家としての命とも言える利き腕を切断した時、治療により髪の毛が抜けた姿を見た時や、日に日に痩せてゆく妻に対して、とても自然で優しく、それでいて力強くて愛に溢れる言葉をかけ続けた。節子はどんなに彼に勇気づけられ慰められただろう。彼の言葉は、一人の女性として私の心にも響き、とても印象に残っている。和気あいあいと家族で食卓を囲んでいる時に、ふと自分が消える寂しさが突然湧き上がる節子。残してゆく子や夫、家族への愛が行間からじんわりと滲みでるように涙を誘う。
本書を読んで実際に彼女の画を見たくなり、大津市の美術館を訪れた。画を前にし、何層にも塗り重ねられた立体的な色づかいや繊細な細い線で描かれていることに驚く。右手で描いた画と比べても遜色ないばかりか、より深く、力強く感じたからだ。彼女が死に対する悲しみや絶望を経験したが所以の人生の深みが現れているからこそ、こうして人の心を打つのだろうと思うと、それもまた、たまらなくやるせなく、切ない。読書でしか経験することのない彼女の壮絶な人生に自分も寄り添うような気持ちで読み進んでいったけれど、寄り添えば寄り添う程、彼女の心情を推し量るには、自分の想像力はまだまだ足りないと思えてならなかった。(本館 二井)
『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(外部リンク) 山口 周/著(光文社)2017年刊 一般書159.4【本館所蔵】
近年グローバル企業が、世界的アートスクールや哲学ワークショップなどに幹部候補生を送り込むことが主流となっている。その理由を著者は、「これまでのような『分析』『論理』『理性』に軸足をおいた経営、いわば『サイエンス重視の意思決定』では、今日のように複雑で不安定な世界においてビジネスの舵取りをすることはできない」ためであり、自分なりの「真・善・美」の感覚、すなわち「美意識」に照らして意思決定をする必要があるからだという。
これは、決して「非論理的」であるということではなく、論理的に考えても判断が下せないような場面に遭遇したときに、自分なりの「美意識」に従い、「超論理的」に判断するということであり、本書では、「美意識」に基づいた意思決定による事例だけでなく、「美意識」の欠如がもたらした事例も紹介している。
その「美意識」欠如の例として、著者はオウム真理教を挙げ、「これほどまでに『偏差値は高いが美意識は低い』という、今日の日本のエリート組織が抱えやすい『闇』」を示しているものは他にないと語る。有名大学出身のエリートが、なぜカルト集団に傾倒したのかという当時の論調に対し、むしろ勉強すればするほど偏差値の上がる受験エリートだったからこそ、教祖に従い修行を積み重ねれば、階位が上がり、解脱できるという単純なシステムに傾斜したのだと、著者は言う。そして、偏差値教育を受けたエリートたちが、「美意識」が欠落した麻原の本を違和感なく受け入れ、同調していったのは、文学に親しむことなく、情緒や感性を育まなかった、すなわち「美意識」を鍛えてこなかったからだと分析している。
著者の主張は、「サイエンス」的な根拠に乏しい部分もあるかもしれないが、列挙される事例には説得力を感じる。本書の出版当時より、世界はますます複雑化し、将来の見通しを立てにくくなっているように思うが、日本なりの「美意識」を鍛えたビジネスリーダーが、必要とされているのかもしれない。 (南館 杉谷)
『本を読んだことがない32歳がはじめて本を読む』(外部リンク)かまど/著、みくのしん/著(大和書房)2024年刊 一般書019.04【両館所蔵】
今までの人生で本を読んだ経験が1度もない人に、もしも本をおすすめするとしたらあなたはいったい何を選ぶでしょうか?
本書は、読書が大好きなかまど氏が、これまで読書をしたことが1度もない友人のみくのしん氏におすすめの本を紹介し、人生で初めて本を最後まで読み切ってもらおうという試みを行った様子をまとめたものです。
国語の教科書に載っていたから記憶に残っているかもしれないという理由で「走れメロス」をおすすめしますが、みくのしん氏の反応は芳しくありません。それでもかまど氏は、なぜ本を読むのが苦手なのか、どうすれば読めそうだと思えるかを丁寧に聞き取りながら、少しずつでも着実に読書を進めていけるよう友人をサポートします。
本書には、本を読むことが苦手だと思う人の正直な心情がわかりやすく提示されています。文字がすり抜けていくような感覚があり読むのが難しい、文章の中にひとつでもわからないことが出てくると気になって読み進められないといったみくのしん氏の意見は、読書に慣れている者にとってはなかなか気づけないことでもあります。
そして、それをしっかり受け止め、友人に合った方法で一緒に読書を楽しもうとするかまど氏の姿勢にも気づかされるところがあります。どれだけ時間がかかってもいいと肯定されることで、読書への苦手意識がほぐれ、みくのしん氏が安心しながら物語の世界に夢中になっていく様子には感動すら覚えます。
かまど氏も驚くほど豊かな感性を活かしたみくのしん氏ならではの初めての読書体験が一体どのようなものになったか、ぜひ確かめてみてください。
本が好きな人にも、そうでない人にも、読書の楽しさが伝わり、何かしらの発見があるのではないかと思える、新たな読書の形を示した作品です。(本館 福田)
『ダメじゃないんじゃないんじゃない』(外部リンク) はらだ 有彩/著(KADOKAWA)2021年刊 一般書914.6ハ【本館所蔵】
日常の中で、別にダメじゃないのになんかダメっぽいと思っていること、ダメと言われてなんとなく守ってしまっていること、逆にぼんやりと誰かにダメと言ってしまっていることがあると感じることはありませんか?
本書は、そんな「ダメ」だと思い込んでいることに対して、「本当にダメなのだろうか」と立ち止まって考えるエッセイです。男の子がコスメと生きることは「らしくないからダメ」? 産休・育休で仕事に穴を開けることは「迷惑だからダメ」? 名前のない関係で生きていくことは「何にもならないからダメ」? など、著者が実際に見聞きしたエピソードをもとに、「別にダメじゃないんじゃない?」という視点で感じたことを自由に綴っています。
ダメじゃないのにダメと感じる状況や背景を、歴史や文化、自身の経験とともに深掘りし、問題に切り込んでいく文章スタイルに、ユーモアあふれる発想やイラストがいいアクセントで、読みやすく、友人と会話をしているようなリラックスした気持ちで、様々な「ダメっぽいもの」について考えることができます。
読んでいると、「これ、感じたことあるな~」と自分の身近な出来事を改めて考えるきっかけになり、そもそも何を基準に「ダメ」なんだろうか、ダメとかダメじゃないとかで決めるものなのだろうか、と深く考えてみたくなりました。「この状況はおかしい」とモヤモヤしたり、怒りを感じることがあるかもしれませんが、本書のコンセプトである「深刻なことをふざけて考えてみる」に倣って肩の力を抜いて考えてみることで、不思議とすっきりした気持ちで「ダメ」と向き合うことができるように感じました。
クスっと笑えてふと考えさせられる、著者の絶妙な視点に触れ、日々なんとなく感じる「ダメ」について、「これって別にダメじゃないんじゃないんじゃない?」と思い始めている自分がいます。(本館 神村)
『幸せってなんだっけ?世界一幸福な国での「ヒュッゲ」な1年』(外部リンク)ヘレン・ラッセル/著,鳴海 深雪/訳(CCCメディアハウス)2017年刊 一般書302.3895【本館所蔵】
世界幸福度ランキングを御存じでしょうか?毎年国連の持続可能な開発ソリューションネットワーク(SDSN)が「世界幸福度報告書」を発行し、世界幸福度ランキングを発表しています。上位を占めるのは「北欧」と総称される、フィンランド、デンマーク、アイスランド、スウェーデン、ノルウェーの国々です。本書は、イギリスの元編集者が夫の転勤を機にデンマークのユトランド半島へ移住し、「ヒュッゲ」と呼ばれるデンマーク由来の生活を体験した日々を綴ったものです。「ヒュッゲ」とは、家族や友人とゆったりした時間を過ごすことや家の中を整えてスローな時間を楽しむこと指します。社会保障の充実、医療費無料、教育費無料などから、デンマークは世界で最も貧富の差が少ない国とされており、2024年の世界幸福度ランキングは第2位でした。(日本は51位)著者はこの国での生活を期待を込めて「デンマーク的生活」と呼び日々を過ごしますが、1日の日照時間が短く、凍てつく長い冬には鬱々とした気分になったり、他国の国旗を掲げて隣人から刑罰の警告を受けたりと、良いことばかりでもありません。その度にジャーナリストとしてのネットワークを駆使して国内の各方面の有識者と連絡を取り、デンマークでの生活の疑問を解決していきます。隣人や有識者たちに、あなたの幸福度は10点満点中何点?と問うと、すべての人が8点以上の高い点数だと言います。お互いを信頼する、誇りを持つ、選択肢を減らしてシンプルに暮らす、おもいっきり遊ぶなど、やりがいのある仕事につき、家族や友人と過ごす豊かな時間がある生活にデンマークに住む人たちは満足しているようです。それはデンマークだけでなく、どの国に暮らしていても自分たちの生活を見つめなおすことで気持ちを前向きにしてくれるとも言えます。あなたの幸福度は10点満点中何点ですか?(本館 塩崎)
お問い合わせ
教育委員会事務局 図書館 市立図書館(本館)
〒525-0036滋賀県草津市草津町1547
電話番号:077-565-1818
ファクス:077-565-0903