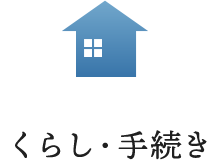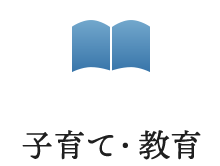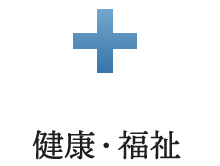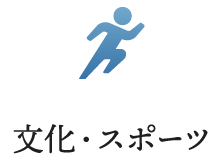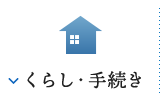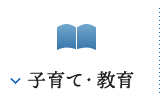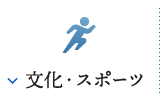避難行動要支援者の避難支援の取り組みについて
更新日:2025年8月22日
草津市では、平成22年5月に策定した「草津市災害時要援護者避難支援プラン全体計画」を令和3年5月の災害対策基本法の改正により「個別避難計画」の作成が努力義務となったことから、令和5年6月に「草津市避難行動要支援者避難支援プラン全体計画」を全面的に改正を行いました。また、令和7年7月に避難行動要支援者登録申請書兼個別避難計画の様式を見直しました。
草津市避難行動要支援者避難支援プラン全体計画(PDF:1,753KB)
避難行動要支援者とは
地域防災計画に基づき、家族以外の第三者の支援がなければ避難できない在宅の人のうち以下の人としています。
- 75歳以上のひとり暮らし高齢者
- 75歳以上の高齢者のみの世帯の人
- 介護保険法で要介護1以上の認定を受けている人
- 身体障害者手帳の1級又は2級に該当する人
- 療育手帳A1又はA2の人
- 精神障害者保健福祉手帳1から3級に該当する人
- 難病患者のうち特定疾患医療受給者等
- 1から7に準じる状態にあり、避難行動要支援者であることを申し出た人
避難行動要支援者登録制度の概要
災害対策基本法に基づき、行政がもつ、住民基本台帳情報や介護情報、障害者情報をもとに避難行動要支援者名簿を作成するとともに、制度への登録をもって個人情報を地域で共有してよいことを本人に確認し、本人の情報や家族等の支援者の情報が記入された個別避難計画を、避難を支援する人や町内会・民生委員児童委員等が共有することで、災害時の安否確認や避難誘導に役立てる取り組みです。
避難行動要支援者は、避難情報など市の情報を把握したり、自力での避難が困難ですので、避難支援者となった隣近所の方が、避難を手助けし一緒に避難します。
また、平常時から、地域福祉の一環として、見守りや関わりを強化してコミュニケーションを図ることが大切です。
個別避難計画について
「個別避難計画」とは、避難行動要支援者一人ひとりについて、災害発生時の「避難支援者」「避難先」「時系列的な避難行動」等をまとめた計画書のことです。
災害時の避難に必要な支援の内容を事前に決めておくことで、避難を円滑・迅速に行うことができます。
- 草津市避難行動要支援者登録申請書 兼 個別避難計画(PDF:570KB)
- 草津市避難行動要支援者登録申請書 兼 個別避難計画(エクセル:15KB)
- 【記入例】草津市避難行動要支援者登録申請書 兼 個別避難計画(PDF:616KB)
また、電子による登録も受け付けております。
下記の「草津市電子申請サービス」ホームページを確認ください。
草津市電子申請サービス(外部リンク)
個別避難計画で決めること
「誰が避難をサポートするか」
対象者が避難する際に避難誘導や安否確認等の支援が必要な場合、ご家族や近隣の地域住民、福祉事業者等の支援を実施する方の氏名や連絡先、住所などを記載します。
「どこに避難するか」
特に避難後の生活において介助等の配慮が必要となる場合、近隣の市が指定する避難所だけでなく、親戚及び知人宅や、地域の避難所、日常利用している福祉施設等も候補に入れて、適切な避難先を選定します。(必要に応じてその経路も検討します。)
「いつ避難するか(時系列的な避難行動)」
気象情報や避難情報を目安とし、いつ避難を完了させるかを事前に決めます。
避難開始までに必要な行動も含めて、当事者や地域がすべき対応を時系列でまとめます。
注:その他、移動の際の持ち出し品や、移動時や生活支援に必要な合理的配慮の内容なども必要に応じて決めておきます。
マイタイムラインを活用しましょう。
現在の市の取り組みについて
国の方針に基づき、市では、令和5年度から令和7年度までにかけて特に支援を要する避難行動要支援者について優先的に個別避難計画の作成を進めております。
併せて、地域や本人が作成する個別避難計画の作成もこれまでの取り組み(災害時要援護者登録制度)と同様に進めています。
委託事業について【委託事業者向け】
令和5年度については、土砂災害警戒区域に居住する避難行動要支援者について、福祉専門職と協力しながら優先度の高い方(ハイリスクの方)について個別避難計画の作成を試験的に進めました。
令和6年度については、浸水想定区域3m以上に居住する避難行動要支援者について、福祉専門職と協力しながら優先度の高い方(ハイリスクの方)について個別避難計画の作成を試験的に進めてまいります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2325
ファクス:077-561-6852