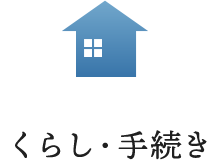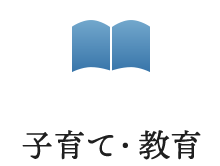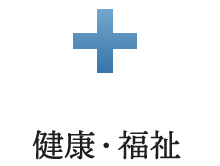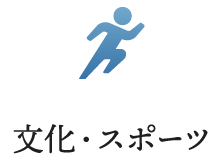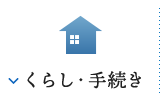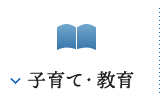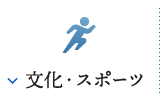ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種(子宮頸がん予防)について
更新日:2025年5月12日
定期の予防接種対象者
定期接種の対象者(経過措置対象者を除く):令和7年度
接種日当日に草津市に住民票があり、小学校6年生から高校1年生相当(平成21年4月2日生まれから平成26年4月1日生まれ)の女性。
経過措置対象者
令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった人がいらっしゃる状況等を踏まえ、 下記対象者は令和7年度に限り、残りの接種を公費負担で接種できます。
- キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性)のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人
- 平成20年度生まれの女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人
経過措置対象期間
経過措置対象者が公費負担で接種を受けられるのは、令和8年3月31日までです。(実施医療機関により最終日は異なります)
HPVワクチンは1回目の接種日が15歳以上となる場合、3回接種で接種完了となり、標準的な接種スケジュールで約6か月かかります。期間内に完了できるよう早めに接種しましょう。詳しい接種スケジュールは医師とご相談ください。
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)予防接種について
子宮頸がんは、ウイルス感染で起こるがんの一つで、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因と考えられています。
このウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスです。
感染しても、ほとんどの人は自然にウイルスが消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。
日本では、毎年約1万人の女性が子宮頸がんになり、毎年、約3,000人の女性が亡くなっています。
そこで、日本では子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐワクチンを提供しています。
HPVワクチンの接種は、平成25年6月から積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、令和4年4月から積極的な接種勧奨が再開されました。
HPVワクチンの種類や接種回数等、詳しくは、下記の厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
![]() 【概要版】女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(2025年2月)(PDF:5,903KB)
【概要版】女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(2025年2月)(PDF:5,903KB)
![]() 【詳細版】女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(2025年2月)(PDF:7,220KB)
【詳細版】女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(2025年2月)(PDF:7,220KB)
HPVワクチンの効果
現在、国内で接種できる子宮頸がん予防ワクチンは、国内外で子宮頸がん患者から最も多く検出されるHPV16型及び18型に対する抗原を含んでいる2価ワクチン(サーバリックス)と尖圭コンジローマや再発性呼吸器乳頭腫症の原因ともなる6型、11型も加えられた4価ワクチン(ガーダシル)、6型、11型、16型、18型に加え31型、33型、45型、52型、58型に対する抗原を含んでいる9価ワクチン(シルガード9)があります。
HPV未感染者を対象とした海外の報告では、感染及び前がん病変の予防効果に関して、高い有効性が示されており、初回性交渉前の年齢層に接種することが各国において推奨されています。
ただし、ワクチン接種を受けた場合でも、免疫が不十分である場合や、ワクチンに含まれる型以外の型による子宮頸がんの可能性もあり得るため、定期的に子宮頸がん検診を受けることが大切です。
接種回数とスケジュール
対象となるワクチンは、(1)「シルガード9」・(2)「ガーダシル」・(3)「サーバリックス」の3種類があります。接種間隔等、ワクチンにより異なりますのでご注意ください。
(1)シルガード9(9価)
1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回での接種完了を可能とする。
ただし、1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけること(標準的な接種間隔では6か月以上あける)。5か月未満である場合は、3回目の接種が必要となる。
1回目の接種を15歳になってから受ける場合
2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種する。(標準的な接種方法)
(標準的な接種方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種する。)
(2)ガーダシル(4価)
2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種する。(標準的な接種方法)
(標準的な接種方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種する。)
(3)サーバリックス(2価)
1か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種する。(標準的な接種方法)
(標準的な接種方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて、2回接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種する。)
注意
- 過去に接種されたワクチンの種類が不明な場合は、接種日当日に住民票があった市区町村にお問い合わせください。
- 1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合は、その翌日(1日)となります。5か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。
HPVワクチンのリスク
- 多くの人に、接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあります。
- 筋肉注射という方法の注射で、インフルエンザの予防接種(皮下注射)と比べて、痛みが強いと感じる人もいます。
- まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。
- 接種後に重篤な症状として報告があったのは、接種1万人あたり、サーバリックスまたはガーダシルでは約5人、シルガード9では約2人です。
接種後に気になる症状が出た場合
接種後に体調の変化が現れたら、まずは接種を行った医療機関の医師に相談し、滋賀医科大学医学部附属病院にご連絡ください。
滋賀医科大学医学部附属病院 患者支援センター
電話:077-548-2515
その他、HPVワクチンに係る相談先、質問・回答などは、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
![]() ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部リンク)
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部リンク)
16歳未満のお子さんが本人のみで受診する場合
13歳以上の場合、本人のみで受診することができます。
- 「予診票」と「保護者の同意書」が必要です。
- 「予診票」は、健康増進課の窓口もしくは医療機関で入手できます。
- 「保護者の同意書」は、健康増進課の窓口、医療機関もしくは下記のURLからダウンロードできます。
- また、事前に下記の予防接種に関する説明文を熟読したうえ、了承された場合は、「予診票」と「保護者の同意書」に保護者の署名をしてください。
- 接種日当日に、保護者の署名がある「予診票」と「保護者の同意書」を、接種する本人が医療機関に持参してください。
- 「予診票」と「保護者の同意書」は、1人1回の接種に対し、各1枚が必要となります。
- 16歳以上のお子さんは同意書は必要ありません。保護者の署名欄には本人が署名してください。
保護者の同伴が必須の医療機関もありますので、本人のみで接種が可能か事前に医療機関へ確認してください。
![]() ヒトパピローマウイルス感染症予防接種 保護者の同意書(PDF:97KB)
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種 保護者の同意書(PDF:97KB)
予防接種実施医療機関について
実施医療機関については、上記リンク先より「さわやか健康だより」8ページから10ページをご覧ください。
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)予防接種の助成(償還払い)は終了しました
子宮頸がん(HPV)ワクチン接種の積極的勧奨を差し控えていたことにより、公費で接種できる機会を逃した方が、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までに自費で接種した場合の接種費用の助成(償還払い)は終了しました。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2323
ファクス:077-561-0180