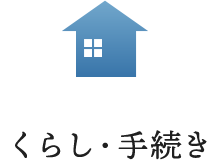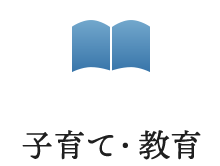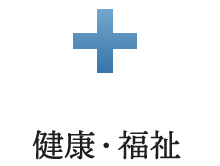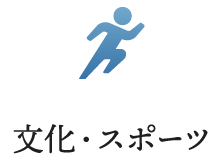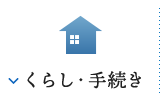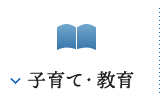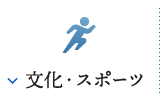2月のアルバム
更新日:2023年3月7日
生活発表会
3歳児
初めて楽器に触れると、音の鳴る面白さを楽しんでいた子どもたち。
発表会ではたのしい手遊びうたに合わせて、カスタネットをたたいたり、鈴を鳴らしたりしました。
劇遊びでは動物になりきって、“お店屋さん”や“ごちそうづくり”の劇をしました。
「〇〇ください」「どうぞ」などの簡単なやり取りを保育者と楽しみました。
はじめての発表会でたくさんの保護者の方に見られて、ドキドキしていた子どもたちですが、楽器遊びや劇遊びがはじまるといつも楽しんでいる遊びということもあり、少しずつリラックスし、いつもの様子を見せてくれました。
4歳児
一つ大きくなった4歳児の子どもたちは、「と と とまと」のリズムに合わせて、鈴・タンブリン・カスタネット・トライアングルでの分担奏をしました。
劇遊びでは絵本『100かいだてのいえ』や今まで楽しんできた“探検ごっこ”を土台に、子どもたちとお話づくりをするところから始めました。
子どもたちと一緒に作ったお話ということもあり、同じ役の友だちと息をぴったりと合わせて、セリフを話す姿がありました。
昨年度は初めての発表会でドキドキしていた子どもたちですが、一つ大きくなり、役になりきって表現することを楽しんでくれました。
5歳児
5歳児にもなると、鉄琴・木琴・大太鼓・小太鼓・シンバル・ハンドベルなどのたくさんの楽器が増えました。どの楽器も一度鳴らしてみて、満足いくまで遊び、最後に発表会で披露したい楽器を決めました。
クラスの仲間と心を一つにしなければ、きれいな合奏は生まれません。何度も練習し、息がぴったりと合うようになってきました。
劇遊びでは、今まで楽しんできた“へなそうる(お話に出てくる動物)”や“忍者と虫”をテーマに子どもたちと一緒にオリジナルストーリーを作りました。
“こんな虫がでてきたらいいな”“へなそうるが困っていたら、みんなで助けたい”など、様々なアイディアが沸いてきました。
そして5歳児は一人一つのセリフを言います。はじめは一人で言うことが恥ずかしい子どももいましたが、劇遊びを楽しむ中で自信を持って言えるようになってきました。
こども園での最後の発表会。緊張や恥ずかしさもありましたが、それを乗り越えて、仲間と一緒にする楽しさ、心を一つにする嬉しさを感じながら、保護者の方に見てもらうことができました。
発表会を終えて・・・
発表会が終わったあとも、劇遊びの他の役がやりたいと話す子どもたちの姿がありました。
自分がやった役だけでなく、役を変わって、友だちがしていた役になりきって、引き続き劇遊びを楽しみました。
改めて保護者の方に見てもらうから頑張るのではなく、表現することを心から楽しんでくれているのだと思います。
その姿を発表会という形で保護者の方に見てもらい、たくさん褒めてもらい、自信になるのだと感じます。
ねずみ大根の土を再利用!
野菜の先生(農林水産課 井上調査員)が園に来てくれました。
ねずみ大根収穫後の土は栄養がない状態です。
野菜の先生が給食センターで作られた堆肥と米ぬかを混ぜたものを持ってきてくれました。
「この黄色の粉(堆肥と米ぬかを混ぜたもの)を土に混ぜると、栄養がいっぱいになるんだよ。そしたら、またこの土でおいしい野菜ができるよ。」と教えてもらいました。
ブルーシートの上に土と黄色の粉をのせて、混ぜていきます。4人一組でバルーンのように混ぜることで、土と上手く混ざり合っていきます。
完成した土は土嚢袋に入れて、1ヵ月置くと、栄養たっぷりの土になります。
ねずみ大根の収穫だけでなく、SDGsに基づき持続可能な社会にしていくために、使用した土の再利用法を教えてもらいました。使ったら終わりではなく、使い続けるためにはどんなことが必要か、子どもたちだけでなく私たち職員の学ぶ機会にもなりました。
老上中学生の作品を見て、触れて
老上(紙)魂としてイオンモールで展示された老上中学校3年生の作品の一部をお借りしました。
すてきな作品の数々に「すごい!」「今にも動き出しそう!」と子どもたちは驚きと興味津々の様子でした。
そーっと作品も触らせてもらいました。
リアルな作品に思わず「(わにの歯が)こわい」なんて声も聞こえてきました。
また保護者の方にも見てもらいました。子どもたちが「みてみて!」「すごいんやで!」「これはペンギン!」とお家の人に話す姿もあり、廃材でできた作品に保護者の方もビックリした様子でした。
中学生の作品を見せてもらい、「お兄ちゃん・お姉ちゃん、すごいなぁ!」と憧れや刺激になった子どもたちでした。